覚えてますか?源頼朝に所領を没収された馬面(うまづら)中原知親の意外な一面【鎌倉殿の13人】

NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」、皆さんも観ていますか?
10月9日(日)本編代わりに放送された「応援感謝!ウラ話トークSP~そしてクライマックスへ~」で、懐かしい顔ぶれが出そろっていましたね。
そんな中、ふと思い出した一人が、森本武晴さんが演じた中原知親(なかはら ともちか)。
初陣で山木兼隆(演:木原勝利)を討ち、勝利を収めた源頼朝(演:大泉洋)たち。その関東支配の第一歩として非道な領主の改易(所領没収)を検討する場面で、名前の挙がったあの男です。
およそ8カ月前の話ですが、もう何年も昔のようですね。
「顔が長いだけでは所領は奪えぬ」頼朝による関東支配の槍玉に頼朝「誰か所領を取り上げてもよい奴はおらぬか」
義時「あの男はどうですか。馬面の」
宗時「ああ、下田を治める中原知親という男がおります。これが、やたらと顔の長い男で」
頼朝「顔が長いだけでは所領は奪えぬ」
義時「平家の家人であることを鼻にかけ、領民の評判も実に悪く、取り立ても厳しい。土地の者は苦しんでいると聞いています」※NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」第5回放送「兄との約束」より
そこでさっそく頼朝たちは知親の所領を没収。鎌倉幕府の公式記録『吾妻鏡』にはこう書かれています。
兼隆親戚史大夫知親。在當國蒲屋御厨。日者張行非法。令悩乱土民之間。可停止其儀之趣。武衛令加下知給。邦道爲奉行。是關東事施行之始也。其状云。
下 蒲屋御厨住民等所
可早停止史大夫知親奉行事
右。至干東國者。諸國一同庄公皆可爲御沙汰之旨。親王宣旨状明鏡也者。住民等存其旨。可安堵者也。仍所仰。故以下。
治承四年八月十九日……※『吾妻鏡』治承4年(1180年)8月19日条
【意訳】山木兼隆の親戚に史大夫知親(さかんのたいふ ともちか)という者がいる。伊豆国で蒲屋御厨(現:静岡県下田市・南伊豆町)を支配し、日ごろ非道な振る舞いによって領民を苦しめていた。
それを停止(ちょうじ)すべく武衛(頼朝)が命令、事務手続きを藤原邦通(ふじわらの くにみち)が執り行う。その書状に曰く
「命令を下す。蒲屋御厨の領民らへ。史大夫知親の支配権を停止する。今後、坂東は武衛が支配すべきことが以仁王(演:木村昴)殿下の宣旨に明らかである。みな安心するように。治承4年(1180年)8月19日」とのことであった。

……大河ドラマではこれ一度きりの登場でしたが、それから知親はどうなったのでしょうか。今回はそんな中原知親を紹介したいと思います。
意外に文武両道だった中原知親中原知親は生年不詳、親戚と言われる山木兼隆との関係も不明です。
元は朝廷に仕えて久安2年(1146年)に文章生(もんじょうしょう。紀伝道の専攻学生)から右少史(うしょうし。史は「ふひと」で書記官)となりました。
生まれつき顔が長かったため、人からは「面長進士(おもながしんし)」と呼ばれたとか。大河ドラマで「顔が長い」と設定されていたのは、ここに由来します。
気を取り直して?久安3年(1147年)に左少史、右大史と順調に昇進。同年12月には従五位下に叙爵した知親。
その才能は文官としてのみならず、仁平2年(1152年)には右兵衛少尉、保元2年(1157年)には左衛門少尉に。文武を兼ね備えた人物だったようです。
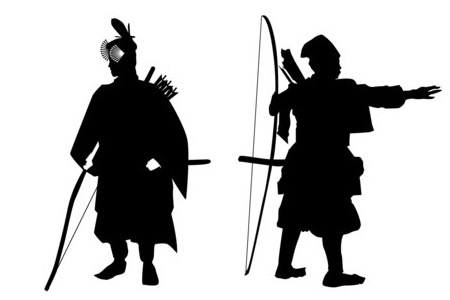
学者として名を高めた知親は多くの弟子に薫陶を与え、また文筆能力を評価されて摂政家の文殿(ふどの。公文所、政所)にも仕えました。
やがて親戚である山木兼隆との伝手か伊豆国へ移住して蒲屋御厨の目代を務めますが、治承4年(1180年)8月に頼朝が挙兵すると所領を奪われてしまいます。
仕方なく京都へ舞い戻った知親は後白河法皇(演:西田敏行)に仕えますが、寿永2年(1183年)に上洛してきた木曽義仲(演:青木崇高)によって解官(げかん。免職)されてしまいました。
これ以降、知親の姿は史料から見えなくなります。特に記録がないことから、義仲が都を追われた後も、政界への復帰は果たせなかったのでしょう。
大河ドラマの都合で仕方ないのかも知れませんが、決してただ暴虐な領主だけではない、意外な一面も見せてほしかったですね。
中原知親こぼれ話山木兼隆の縁者 中原知親
森本武晴
伊豆国司の目代・山木兼隆の縁者。顔が長いのが特徴。※NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」公式サイト(人物紹介)より
以上、中原知親の生涯を駆け足で辿ってきました。最後に彼の特徴である顔の長さにまつわるエピソードを一つ。
史大夫朝親ト云者アリケリ、学生ナリケレハ此彼ニ文師ニテアリキケリ、若クテ文章生ニテ有ケリ、事ノ外カホノ長リケレハ、世人長面進士トソ云ケル、世ノ常ナラスオコヒタルモノ也、或時知タル僧ニ輿車ヲ借テ物ヘユキケル程ニ、車ヒキカリケレハ烏帽子ヲ取テ手ニモチタリケリ、サテヒカレ行程ニ法性寺殿御アリキニ参会テマトヒオリケル程ニ、彼モチタル烏帽子ノ事ツヤツヤ忘ニケリ、下テ後ハ小家ナトニモ入ルヘキニ、我ハ文殿ノ衆ニテオノツカラ御書沙汰ノ時ハ参レハトテ、大路ニウスクマリ居タリケリモトトリハナチタル者ノ右ノ手ニ烏帽子サケタリ、オホカタ御前ノ御随身オトカイヲハナチテ咲ヒケリ、
※『十訓抄』より
【意訳】史大夫朝親(知親)という者は学生(がくしょう)として名高く、あちこちで学問を教えていた。
若くして文章生(進士)となるほど優秀であったが、ことのほか顔が長かったので、人々は長面進士とあだ名している。
ある時、輿車(こしぐるま)を借りて外出中、その天井が低かったので頭がつっかえないよう烏帽子を外していた(どうせ外からは見えないのだから、問題なしと判断したのであろう)。
するとそこへ法性寺殿(ほっしょうじどの)こと主君の藤原忠通(ふじわらの ただみち)がやってきたので、烏帽子を脱いでいることも忘れて腰から飛び出してしまったのである。
終わりに
「……あ」
後はお察しの通り、丸裸の頭髪を衆目に晒し、失笑(というより大爆笑)されてしまったのです。原文「顎(おとがい。アゴ)を(解き)放ちて咲(笑)いけり」という表現が、知親の恥ずかしさを物語ります。
大河ドラマの一幕々々に消えて行った脇役たちも、調べてみるとこうした興味深いエピソードがたくさん。他の者たちについても、改めて紹介して行けたらと思います。
※参考文献:
五味文彦ら編『現代語訳 吾妻鏡 1頼朝の挙兵』吉川弘文館、2007年11月 田中健三『詳註新撰 十訓抄』当倫書房、1931年4月 笹川種郎ら編『史料大成 第23』内外書籍、1935年7月日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan













