平安アーティストの頂上決戦!日本史上最古の画家・百済河成vs飛騨工のエピソードを紹介
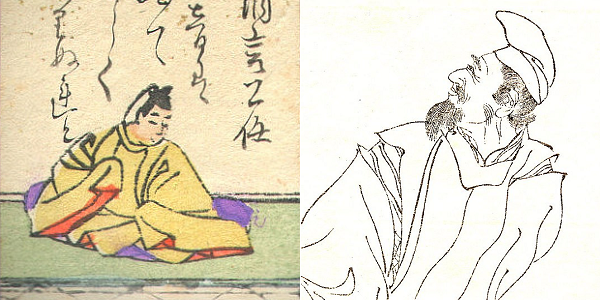
日本史上、名前が伝わっている最古の画家は百済河成(くだらの かわなり)と言うそうです。
現存する作品はないものの、数々の伝説を残す名匠でした。
河成の描いた絵はまるで本物さながら。川を描けば水が流れ、せせらぎが聞こえんばかりだったと言います。
今回はそんな河成と、彼とライバルだった飛騨工(ひだのたくみ)のエピソードを紹介。
飛騨工も相当ハイレベルなアーティストだったそうですが、どんな闘い?を演じてくれるのでしょうか。
第1ラウンド・どの扉からも入れない!
ある日のこと。飛騨工が河成を自宅に招きました。
「やぁ、今日はお招きありがとう」
「いやいや、こちらこそ来てくれてありがとう。君に是非とも見てほしい作品があってね」
「そうかい。それは楽しみだ」
飛騨工は平安京遷都の際、豊楽院(ぶがくいん)を造営。その名を天下に轟かせた建築家でもあります。
「して、作品はどこにあるんだい?」
「庭に小さな堂を建てて、その中に納めてある。もてなしの用意をしておくから、先に行って見ていてほしい」
「分かったよ」
さて、河成が庭に出ると、相変わらず見事にあつらえてありました。その片隅に、小さな堂が建っています。
「やぁ、これはたいそう見事だな」
堂は東西南北に扉がついており、すべて開け放たれています。
さっそく河成が南の扉から入ろうとすると、どういうわけが扉がひとりでに閉じてしまいました。
開けようとしても開かないので、仕方なく西側へ回り込みます。
すると不思議なことに、今度は西側の扉がひとりでに閉じてしまい、南側の扉が開いたではありませんか。
西側の扉が開かないので、今度は北側の扉に回り込んだ河成。しかし又しても北側の扉が閉じて、西側の扉が開いたのでした。
河成はだんだんイライラしてきます。急いで東側の扉へ回り込むと、もう予想どおり東側の扉が閉じて、北側の扉が開きました。
「もう、訳が分からん!」
堂に入ることをすっかり諦めた河成。縁側より庭に下りると、飛騨工が大笑いで言います。
「やぁ、引っかかったね。君に見てほしかったのはこの堂さ。どうだい、見事なカラクリだったろう?」
扉がひとりでに開いたり閉じたりする仕掛けをしておいた飛騨工。もくろみが成功して大満足でした。
ちなみに南側の扉が閉じた時、時計回り(西側)でなく反対回り(東側)も試したのでしょうか。
ともあれ一杯食わされた河成は、プリプリして帰ったのでした。
第2ラウンド・河成の意趣返しそんな事があって、しばらく経ったある日のこと。飛騨工のもとへ、河成からお誘いがありました。
「見せたいものがあるから、ぜひ遊びに来てほしい」
いやいや、先日あんなことをしたものだから、意趣返しに決まっているじゃないか……その手には乗らんと誘いを断り続けました。
しかし河成が何度も誘ってくるので、断りきれずに訪問します。
(さぁ、一体何をしかけてくるのか……)
「よく来てくれたね。最近、新作の絵が仕上がったんだ。その戸を開けて見ておくれ」
この戸を開けたら何が飛び出すのか……飛騨工はなかなか戸を開けることができません。
そんな様子を見て、河成は言います。
「疑っているのかい?ひどいな。本当に自信作なんだ。一番の親友である君に、誰より早く見て欲しかったんだ。さぁさぁ、どうか見届けておくれ」
そこまで言われたら仕方ありません。思い切って戸を開けると、飛騨工は衝撃の光景を目の当たりにしました。
「あなや!」
何とそこには死体が転がっており、鼻を刺すような死臭が充満しているではありませんか。

「そなた、何ということを!」
今にも嘔吐しそうな顔で、何とか声を絞り出して河成を非難する飛騨工。
いくら驚かそうと言っても、こんなものを用意するなんて、頭がおかしいとしか思えません。
しかし飛騨工がどれほど声を荒らげても、河成は平気な顔をしています。
まったく、どれほど神経が図太いのか……河成は飛騨工にタネ明かしをしたのでした。
「君は勘違いしているようだけど、そこにあるのは死体じゃなくて、ただの絵だよ」
いや、そんなはずはありません。なぜならさっき鼻を突き刺すような死臭が……。
「疑うなら、もう一度絵を見て、よく嗅いでごらん。匂いなんて一切しないから」
飛騨工が恐る恐る見てみると、確かに絵だったのです。
「これはまた、まるで本物のようだ……しかし、先ほどは死臭が確かにしたんだ!」
「それは君がこの死体の絵を見て、頭の中で匂いを連想したんだろうな。要するに気のせいってヤツさ」
死体があるなら、死臭がただように違いない。そういう思い込みが幻覚で鼻の奥に匂いを感じさせたのでしょうか。
もしそうなら、河成の絵がいかにリアルであったかを物語るようです。
これは実に見事な意趣返し。飛騨工は感心して帰途についたのでした。
現代に伝わる名古曽滝ちなみに河成は造園にも心得があり、嵯峨院の造営に際して滝殿の石組みも造り上げました。
この滝は名古曽(なこそ)滝と呼ばれましたが、平安中期には涸れてしまったそうです。
が、名古曽滝は永く愛され続け、その美しさを詠んだ有名な和歌が現代に伝わっています。
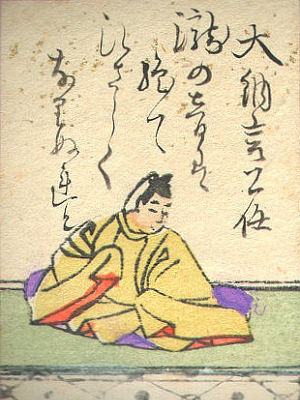
滝の音は たえて久しく なりぬれど
名こそ流れて なほ聞えけれ
「小倉百人一首」でも有名なこの和歌を詠んだのは大納言公任(だいなごん きんとう)の名で知られる藤原公任です。
【意訳】滝の水が涸れて、その音も聞こえなくなって久しい。しかしこの美しい滝を造った河成の名声は、今も聞こえ続けている。
「な」こそ「な」がれて「な」ほきこえけれ、という音の軽妙なつながりがいいですね。
この名古曽滝は千年以上の歳月を経た大正11年(1922年)に国の名勝「大沢池 附 名古曽の滝跡」として指定されました。
また平成6年(1996年)から発掘調査が行われ、中世の遣水(やりみず)遺構が発見されます。
そして平成11年(1999年)に復元完了。河成の名を一層高めることになったのでした。
終わりに以上、『今昔物語集(百済川成と飛騨の工と挑みし語)』より百済河成と飛騨工のエピソード+αを紹介してきました。
二人の頂上決戦?は一勝一敗の引き分けといったところでしょうか。
名古曽滝が現存している分だけ、河成の判定勝ちとしてあげたいところです。
他にも百済河成や飛騨工の作品が発見されないか、今後の探求がまたれます。
※参考文献:
宝賀寿男『古代氏族系譜集成』古代氏族研究会、1986年4月 森田悌『全現代語訳 続日本後紀 下』講談社学術文庫、2010年10月日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan













