鎌倉幕府の公式記録『吾妻鏡』は北条氏による歴史の捏造!?鎌倉時代の通説を覆す数々の学説

北条氏の権力掌握
北条氏は、系図や鎌倉幕府が著した『吾妻鏡』によると、桓武平氏の流れを汲むとされています。
ただ、後に初代執権となる時政以前の系譜はよく分かっていません。伊豆を拠点にした中規模の武士団だったと考えられている程度です。

その北条氏は、1199年に源頼朝が死去してからさらに権力を強めます。政子の長男・頼家が10歳代後半で家督を継ぐと、時政は有力な御家人計13人による合議制で政治を行うようになりました。
御家人による勢力争いが激しくなる中、1203年に北条時政は2代将軍の頼家を廃し、3代将軍に弟の実朝を就け、自らは幕府の政務をつかさどる政所筆頭の長官(執権)となります。
その息子で2代執権となった義時は13年、御家人を統制する侍所長官だった和田義盛を合戦で滅ぼしたことで権力を掌握しました。その後、執権は北条氏一族で世襲されるようになったのです。
将軍は傀儡ではなかったこうした経緯を踏まえて、これまでは頼家と実朝は北条氏の傀儡と見られがちでした。
ところが、これは『吾妻鏡』によりかかった説であり、貴族の日記や他の史料なども調べていくと、頼家は御家人と貴族の間の所領をめぐる訴訟などでは公正な裁きをしていたことが分かります。
また実朝はそれに加え、街道の整備や軍馬の育成など、きちんと将軍としての務めをしていました。

『吾妻鏡』は、主に北条氏の全盛期である13世紀後半に幕府側の視点で編纂されました。源頼朝の正しい政治を継いだのは頼家や実朝ではなく北条家だったというという筋書きにした可能性は大いにあります。
特に、3代執権の泰時を正統な後継者にしようと史実を脚色したふしもみられます。
2022年のNHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』でも、義時がなぜ最後に実権を握れたのかが、ドラマの大きなテーマになっていました。
これは、彼が頼朝の御台所だった政子の弟であることも大きいのですが、合戦の時も情勢分析に長けていた戦略家だったという点がポイントです。
武士と貴族の関係また、鎌倉初期は武士と貴族が対立していたというイメージがありますが、必ずしもそうではありません。
武士たちは自らの勢力を維持拡大するために朝廷の官位を望み、頼朝は将軍の推挙を受けた武士に官位を与えることで全国の治安維持を担わせていました。
武士の側も朝廷の側もお互いにうまく利用し合うことで、幕府と朝廷はうまくバランスを取っていたのです。
それが崩れたのが1219年の実朝の暗殺です。実朝が頼家の子に殺されたことで朝幕関係は不安定にり、承久の乱のきっかけになりました。
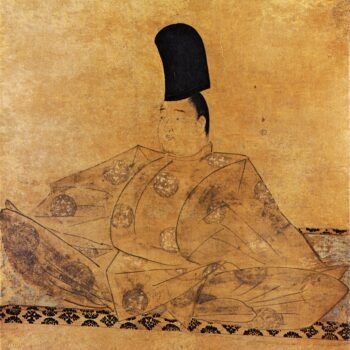
この乱では、北条政子による東国の御家人の説得が成功して上皇側を破り、後鳥羽ら3人の上皇が配流されたことで幕府の権力が強まりました。
こうしたきっかけがあって朝廷の勢力は低下したのであり、最初から武士と貴族が対立していたわけではなかったのです。
参考資料:
中央公論新社『歴史と人物20-再発見!日本史最新研究が明かす「意外な真実」』宝島社(2024/10/7)
画像:photoAC,Wikipedia
日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan













