法改正で支払額100万円アップ!国民年金納付64歳まで延長!生活は こう変わる素朴な疑問20
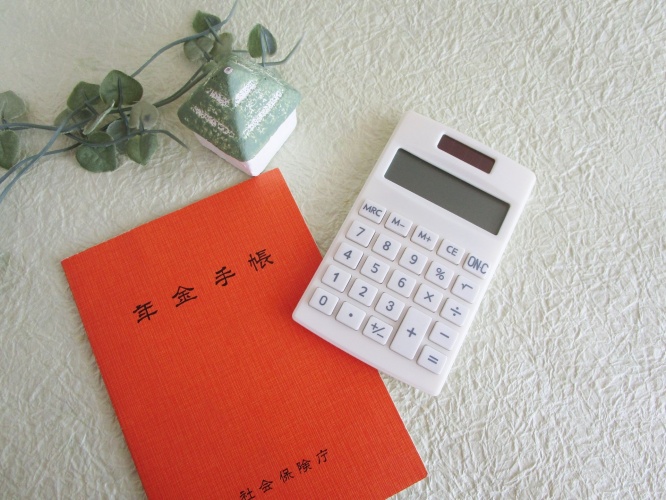
晩年を支えてもらおうと、払ってきた金が、もらえる時期が遠のくピンチ。どういうことか。プロを直撃!
「またも、庶民から金をむしり取るつもりか!」
政府の社会保障審議会が国民年金保険料の納付期間を5年間延長する方針を示したことで、巷ではこんな怒りの声が噴出している。
「この案が実現すると、これまで20歳から59歳までだった保険料の納付義務が64歳まで続き、その5年間でおよそ1人当たり100万円の負担増となることが懸念されています」(全国紙政治部記者)
その年金制度法だが、2年前に改正され、今年4月から新制度が始まっている。
「国民から100万円をぶん捕ろうとする政府のことだから、国民の知らないうちに年金制度を改悪しているのではないか」
そんな疑念を抱く声も噴出中だ。
いったい、老後の暮らしは、どうなってしまうのか。改めて、年金についての不安や疑問にゼロからお答えしよう。
■Q.支払い額100万円アップは本当か?
A.「おそらく、そうなります」と語るのは経済アナリストの森永卓郎氏だ。その根拠は明確だ。そうしないと月5万円の年金受給額を死守できないからだという。
「経済成長の停滞や、少子高齢化の進行などといった最悪の状況が今後も続いた場合、30年後に国民年金の給付額が月3万9000円まで減るという推計があります。さすがに、その金額では暮らせませんから、年金納付期間の延長の議論が出てきたわけです」(前同)
つまり、納付期限を64歳まで延長すると保険料収入が12 .5%増えるため、なんとか5万円台の給付をの維持できるというのが政府の皮算用のようだ。
「確かに月3万9000円より5万円のほうがマシです。とはいえ、現在の国民年金の受給額が月6万5000円弱という水準なので、将来的にはおよそ1万5000円も受給額が減ることになります」(同)
その皮算用で、国民の負担が増えるのは必至だ。
「一般的な60代前半夫婦の家庭でそれぞれ100万円ずつ(計200万円)という大きな負担を強いられた結果が“年金の目減りを頑張って減らしました”で、はたして国民が納得するでしょうか」(同)
■Q.失職などで年金が払えなくなったら、どうなる?
A.年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金の2階建てで構成され、60歳から追加負担となる見込みの国民年金は1階部分の老齢基礎年金にあたる。会社員は、それにプラスして2階部分の老齢厚生年金を受給できる。その1〜2階を合わせて老齢年金と呼んでいる。
「その老齢年金には繰り上げ受給が認められています。65歳からの受給が原則ですが、60歳へ繰り上げての受給も可能です。この制度を利用すれば、仮に60歳で定年を迎え、再雇用を受け入れずに無職でいても、年金をもらうことができます」(転職情報誌ライター)
■Q.繰り上げて受給すると損をする?
A.早く受給できる分、年金額そのものが減額になる。
「今年3月までは、減額率が1年につき0.5%でした。65歳からの老齢基礎年金の額が年180万円として計算すると、60歳からの繰り上げ受給を選択した場合、年金額は126万円になります。結果、1年間で54万円も損する計算になります」(前出の政治部記者)
ただ、4月から、この減額率が0.4%と、65歳から支給される年金額との差がわずかに縮まった。それでも先ほどのケースで、65歳からの年金額180万円と比べると、43万円減の137万円になってしまう。
「ただ、1962年4月1日以前に生まれた人の場合は、減額率は従来の0・5%が適用されます。繰り上げ受給を選択すると、長生きすればするほど損する形になりますね」(前同)
長生きすることに自信があるなら、繰り下げ受給を選択すべきだろう。これまで70歳までだった繰り下げ受給の年齢は、4月から75歳まで引き上げられている。
「毎月0.7%増額されるので、限度いっぱい75歳まで繰り下げると、年金額は84%も増えることになります」(同)
年金問題に詳しい、ファイナンシャルプランナーの長尾義弘氏が解説する。
「繰り下げを選択すべきかどうかの損益分岐点は“プラス約12年”。つまり、87歳以上生きる自信があれば75歳まで繰り下げ、そこまでは無理としても、82歳までならいけると思ったら、70 歳までの繰り下げを選択するといいでしょう」
70歳への繰り下げでも年金額は42%も増える。
■Q.将来的に年金受給額は減るのか?
A.残念ながら、減ることも予想されるという。前出の森永氏が解説する。
「国民年金の支給額が月5万円になるという推計は、先述の通りです。加えて、厚生年金も、月21万円(受給平均世帯の夫婦合計年金額)が30年後、月13万円まで下がるという推計があります」
減額される理由の一つには、「マクロ経済スライド制度」がある。物価や賃金などが上昇しても、調整が入り、支給の伸びが抑えられるという制度だ。ちなみに、今年度の基礎年金額は、この制度によって昨年度より0.4%減額されている。
一方、生活は維持できるという声もある。
「所得代替率といって、政府は現役世代の平均年収を基準に年金支給額を設計しています。現在の所得代替率は現役世代の6割台を維持。どれだけ下がっても5割は維持できる見通しです」(前出の長尾氏)
年金を受給する際、現役バリバリで働いている世代の半分の年収は確保できる計算だという。
■Q.未納者が2割もいるが、本当に大丈夫なのか?
A.年金は破綻しないというのが、専門家の共通認識だが、未納者が多くなれば、年金制度は維持できなくなるはず。
「確かに国民年金の保険料未納者が2割いるのは事実です。一方、厚生年金の保険料は給料から天引きされますから、未納はほぼ起きません。国民年金に限れば高い割合に思えますが、全体で見ると、年金保険料の未納者は2%弱に過ぎないんです」(前同)
■Q.年金運用に国が失敗したという話をよく聞くが、大丈夫か?
A.年金を支給するための財源は3つある。
「まず1つ目は、国民が支払う保険料で、およそ39兆円。2つ目が国庫からの支出で、およそ13兆円。そして、3つ目がGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の運用資金です」(全国紙経済部記者)
よくマスコミで「赤字になった」と報じられるのはこのGPIFの運用資金だ。
「運用が悪いと報道され、良いときには報道されないので、運用に失敗しているという印象を抱きがちですが、累積では100兆円以上の黒字になっています。仮に年金給付のために、ここから取り崩したとしても、運用益の部分で事足りるため、元本は手つかずで残ります。そもそもGPIFの運用資金は年金の1割に過ぎず、もしも運用成績が急激に悪化しても、年金を支払えない事態には陥りません」(長尾氏)
■Q.お得な年金保険料の支払い方はあるか?
A.国民年金加入者の場合、“早割”を活用したい。
「早割、つまり年払い(前納)を選択すると、月払いより、かなりお得になります。令和4年度の場合、1年分を前納すると年間で3530円、2年分をまとめて前納すると、1万4540円の割引になります」(生活情報誌記者)
クレジットカードの使用が可能になったので、支払いの際、カードにすると、ポイントも稼げ、割引分と合わせて、ダブルでお得になるのだ。
■Q.社会保険庁から送付される公的年金の保険料納付実績や将来受給できる年金額の見込みなど、年金に関係する個人情報の通知書である「ねんきん定期便」。どう見たらいいのか?
A.50歳未満の人と50歳以上の人では、内容が違う。
「50歳未満の人の場合、記載された年金額は、それまでの支払い実績に応じたものですから、かなり小さな金額になっています。しかし、実際の年金額とは違うので、安心してください。一方、50歳以上の人の数字は見込み額ですので、記載された数字が、ほぼ自分の年金額だと思ってください」(長尾氏)
ただ、その場合も、前述のマクロ経済スライドや年収の増減などで、実際の年金額は変動するという。
■Q.未納者には差し押さえがあるのか?
A.「著名な作家が突然、銀行預金2000万円以上を差し押さえられたというニュースがありました。年間所得300万円以上かつ未納期間7か月以上が、国民年金の差し押さえ基準なので注意しましょう」(全国紙社会部記者)
■Q.2024年度の法改正で何が変わるのか?
A.焦点は財政基盤の弱い国民年金(老齢基礎年金)がどう変わるかだが、厳しい結果になりそうだ。
「今回の年金納付期間の延長の議論で政府が発したメッセージは、“今後は、定年後に悠々自適な生活は許されない、働きなさい”ということ。
極端に言うと、定年後にのんびり暮らすヤツから、“夫婦合わせて200万円(納付期間延長分の保険料)の罰金を取るぞ”ということです」(森永氏)
老後の悠々自適な生活は、もはや日本には存在しないようだ。
■いまさら人に聞けない!「国民年金」素朴な疑問Q&A
Q:年金手帳を紛失した場合は?
A:今年4月から年金手帳の新規交付・再交付が廃止に。紛失した際は年金事務所へ届け出て“基礎年金番号通知書”を受け取ろう。それが手帳代わりになる。
Q:そもそも年金の仕組みは?
A:労働を担う現役世代(20歳以上60歳未満)が支払った保険料などで確保した財源をもとに、高齢者などへ生活を支えるための“年金”を給付する制度。
Q:保険料はどうやって決まるのか?
A:国民年金は年齢や収入に関係なく一律金額。厚生年金は給与に応じた32等級の“標準報酬月額”に、18.3 %の保険料率を掛けた金額が保険料となる。
Q:「iDeCo(イデコ)」って何?
A:任意で加入できる私的年金制度。20歳以上65歳未満の間に拠出した掛金を自分で運用し、その運用益を60歳以降に“老齢給付金”として受け取れる。
Q:標準報酬額はいつどのように決まる?
A:4、5、6月の3か月間分の給与(通勤、残業などの各種手当を加えた総支給額)を割った平均が、“標準報酬額”となる。毎年1回、見直される。
Q:「iDeCo」は入るべき?
A:公的年金の受給額の縮小などに備えて老後資金を確保したいという人向け。また、「iDeCo」の掛金、運用益には税制優遇があるので節税効果も高い。
Q:「ねんきんネット」って何?
A:日本年金機構が運営する、24時間ネット上で年金記録の確認などができるサービス。基礎年金番号、メールアドレスがあれば、誰でも簡単に登録が可能。
Q:2022年4月から何が変わった?
A:65歳未満受給者の在職老齢年金制度の支給停止基準額を47万円に緩和。65歳以上の高年齢労働者には年に一度、年金が増額する在職定時改定が導入された。
Q:払うと損するって本当?
A:現行の保険が維持された場合、国民年金・厚生年金ともに支給開始から約10年を超えると、支払った金額以上の年金が受け取れるので、損するとは言えない。
Q:2022年10月から何が変わった?
A:個人経営の職場の就労者や、アルバイトなどの短時間労働者の厚生年金への適用範囲が拡大された。これまで配偶者扶養で免除されていた主婦も要注意だ。













