語尾の「ですわ」、使うのはお嬢様?関西人? 言葉の違い、マジメに調べてみた (1/2ページ)
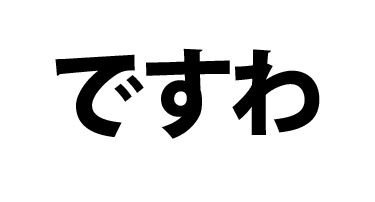
礼儀正しいお嬢様と、関西弁を話す気さくなおっさん――。正反対にも思えるこの2人の話す言葉が、文字にしてみるとソックリだというツイートが、先日ネット上で注目を集めていた。
お嬢様「なんですの?」
関西弁のおっさん「なんですの?」
お嬢様「いいですわ」
関西弁のおっさん「いいですわ」
お嬢様「よろしい」
関西弁のおっさん「よろしい」
お嬢様「私をこんな目にあわせるなんて屈辱ですわ」
関西弁のおっさん「私をこんな目にあわせるなんて屈辱ですわ」
- 独雄 (@docuwo) 2019年2月1日
二つの「ですわ」にどんな違いがあるのか、それぞれの言葉のルーツを調べてみると日本語の面白い世界が見えてきた。
お嬢様「ですわ」のルーツは?まず「ですわ」を分解してみると、助詞の「です」と「わ」に分かれる。注目したいのは、語尾の「わ」のアクセントだ。
この「わ」には上昇調と下降調のアクセントがあり、上昇調だと女性的、いわゆるお嬢様言葉やオネエ口調に。下降調だと関西弁となる。文字にすると同じだが、お嬢様と関西弁では、そもそもアクセントに違いがあるわけだ。
ですわを調べてみた
続いて、それぞれの言葉のルーツを探って行こう。まずはお嬢様言葉の「ですわ」から。
「わ」が女性語として定着し始めるのは明治時代に遡る。近代教育制度が始まると、東京を中心に女子教育のための女学校が開設されていった。この学校に通う生徒たちの間で「よろしくてよ」「だわ」など、いわゆる女性語表現が形成されていったという。
ちなみにこのような「てよだわ」言葉、実は明治時代に流行が始まった頃は「下品」とみなされていたそうである。今でいうギャル語のような扱いだったわけだ。その後少女雑誌などを通じて戦前には女学生など都市部の教養ある女性の言葉遣いとして定着した。
当時の女学生や有閑マダムといえば華族や富裕層の子女であったから、れっきとしたお嬢様育ち。













