着物の柄から絵師・鈴木春信の代表作「風俗四季哥仙」を読み解く!春信の魅力 その4【後編】

前回ご紹介した「風俗四季哥仙 弥生」その4【前編】に続き、今回は後編をご紹介します。
前回の記事はこちら
3月3日は曲水の宴?絵師・鈴木春信の代表作「風俗四季哥仙」から日本文化を探る!春信の魅力 その4【前編】 古典文学が後の世に与えたもの
鈴木春信 風俗四季哥仙 弥生 (出典:国立博物館所蔵品統合検索システム)
さて、「風俗四季哥仙 弥生」をじっくり観てみますしょう。まず目につくのは桃の花。今が天下と咲き誇っており、“桃の節句”と言われたのも理解できます。
絵の中ほどに曲がりくねった小川の上を盃が流れています。
奥にいる黒い羽織を着た男性が今にも和歌を詠もうとしているかの様子。子供が硯を差し出しています。ちなみに江戸時代には羽織は男性だけが着ることができるものでした。

流れの下流には二人の女性がいます。立っている女性が着ている着物の模様はアヤメでしょうか?それともショウブか杜若?
皆さんも「いずれアヤメかカキツバタ」というフレーズを耳にしたことがあるかもしれません。これはこの花の見分けがつきにくいということから転じて、“どちらも優劣がつけ難い”という意味です。
着物の柄に「杜若(かきつばた)文様」または「八橋文様にかきつばた」という絵柄があります。これらは全て「伊勢物語」を踏まえて描かれた文様です。
「伊勢物語」は平安時代、奔放な人生を送ったとされる天才歌人・在原業平をモデルに、主に恋愛を含めたさまざまな内容が、和歌を中心に語られた歌物語です。
その中のある場面で、身分違いの恋に破れた男が都を下って流浪する最中、三河の八橋の沢を通ります。すると杜若(かきつばた)の花があちらこちらに美しく花を咲き誇らせていました。
男はその美しい光景を目にして郷愁の念にかられ歌を詠みます。
か 唐衣
き 着つつなれにし
つ 妻しあれば
ば はるばる来ぬる
た 旅をしぞ思ふ
句頭に“かきつばた”という言葉を入れた折句にもなっており、「伊勢物語」の名場面の一つとされています。
「伊勢物語」は「源氏物語」にも影響を与えたと言われ、江戸時代に多くの人に愛読されました。そして着物の柄に杜若や川の流れ、または八橋などが描かれていると『あ、これは伊勢物語の・・・』という風に読み取られる訳です。
このようなことは鈴木春信も知っていたでしょう。ですから“曲水の宴”から“川の流れ”→“杜若”と連想したことは想像にやすく、この着物に描かれた花は“杜若(かきつばた)”と考えられます。

座っている女性が着ている着物の柄は“わらび柄”だと思われます。
この柄は中年以上の女性が着用するものと言われています。中年女性を“年増女”とするならば、江戸時代には“数え20で年増、25で中年増、30で大年増と呼んだ”ということですので、この女性の年齢はまだ二十歳そこそこで少女の世話役の女性でしょう。

世話役の女性が、良家の子女と思われる少女に“和歌が詠めなかったら、あの盃のお神酒を飲まなければ”と声をかけている。
良家の子女である少女は“そんなお酒を飲むなんて嫌だわ”とでも言っている様子です。もしかするとこの少女は“曲水の宴”に出席するのは初めてなのかもしれません。
奥にいる子供は、この二人の女性の成り行きを興味ありげに眺めているようにも見えます。
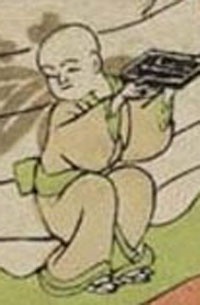
実際に“曲水の宴”が若い男女の出会いの場ではなかったとしても、鈴木春信はそのような設定にしたかったのかもしれません。何故ならその方が面白いから。浮世絵は事実をそのままに写し取るものではなく、作者の感じる世界を創造して描かれています。
さて、平安時代に盛んに行われていた“曲水の宴”は、鎌倉時代からいわゆる戦国時代にかけて、断絶しました。
ところが江戸時代半ばの享保17年(1732年)に、8代将軍徳川吉宗が故実を調べて曲水の宴を江戸城で再興したのです。
江戸の庶民は300年以上も前に貴族の間で行われた“曲水の宴”など知るよしもないはずです。
そこで、鈴木春信は「風俗四季哥仙 弥生」の題材として、弥生=三月の三日に行われていた、“曲水の宴”を選んだのではないでしょうか。昔、そのような“雅な宴”が初春に行われていたのだという事実は、春を迎える人々の高揚感を更に高めるものだったでしょう。
おわりにさきほど“浮世絵は事実をそのまま写し取るものではない”と述べましたが、例えば「風俗四季哥仙 弥生」で描かれる曲水の宴では、家紋を染め抜いたと思われる幕が張られています。
しかし“曲水の宴”でそのようなしつらえをすることは無かったと思われます。またその一方の幕には「六角に三つ柏」という“桓武平氏”系の家紋が、もう一方には「竜胆(リンドウ)紋」という“村上源氏系”の家紋のようなものが染め抜かれています。
これは一体何を意味するのか。鈴木春信のたくらみがここにも隠されているのかもしれません。
次回は“風俗四季哥仙 (その5)”に続きます。
日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan














