ラスボス感ハンパない!色んな意味で強かった?毛利元就の愛娘・五龍姫の生涯
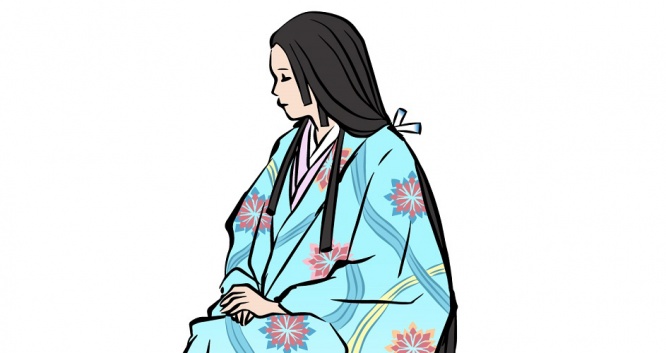
古来「名は体(たい)を表す」とはよく言ったもので、名前はその対象をよく表し、またそうなるように影響しやすいものです(※中には「名前負け」という例外もありますが)。
今回紹介したいのは中国地方を代表する戦国大名・毛利元就(もうり もとなり)の愛娘である五龍姫(ごりゅうひめ)。
その文字面を見た瞬間「恐ろしげな五頭の龍を手足のごとく従え、勇者の前に立ちはだかる魔王」のような女性を想像してしまいましたが、いったい彼女はどんな人生を歩んだのでしょうか。
長女の悲劇を繰り返すまい……両親の愛情を一身に受けた少女時代五龍姫が生まれたのは戦国時代の享禄二1529年、毛利元就とその正室(本名不詳。後に出家して妙玖と称す)との次女として生まれました。本名は「しん」と言うそうですが、便宜上「五龍姫」で統一します。
姉である長女は戦国の習いとて、幼いころ石見国(現:島根県西部)の国人・高橋氏へ養女(実質的には人質)に出され、後に元就が高橋氏を滅ぼした際、最後の当主・高橋大九郎興光(たかはし だいくろうおきみつ)によって殺されてしまいました。
いくら政略とは言え、可愛い我が子(ましてや女の子)の悲しい最期を悔やまずにはいられない親心……という訳で、残った次女にはそんな思いをさせまいと、元就夫婦は五龍姫を溺愛したと言われています。

とは言え、いつかはお嫁に出してやらねば……という事で、長女の悲劇を繰り返さぬよう、領土が隣接している宍戸(ししど)氏の嫡男・宍戸弥三郎隆家(やさぶろうたかいえ)に嫁がせて代々の抗争関係を和解、同盟関係を築きます。
時に天文六1534年、五龍姫はまだ6歳、宍戸隆家も17歳。初々しいと言うより「妹のおままごとにつき合ってあげる兄」みたいな歳の差夫婦でした。
かくして宍戸氏の本拠地・五龍城(現:広島県安芸高田市)の方へ嫁いだ事で、姫は「五龍の方」「五龍の局」と呼ばれるようになり、元就など親しい者は「五もじ(文字)」などとも呼んだそうです。
龍のように激しかった?一族の繁栄に貢献するも……さて、五龍姫と宍戸隆家との夫婦仲は良好だったようで、二人の間には一男三女が生まれました。
まず長男の弥三郎元秀(もとひで。弥三郎は代々襲名)は宍戸家の跡取りとして確保、長女は伊予水軍の棟梁・河野通宣(こうの みちのぶ)に嫁がせることで瀬戸内海に勢力基盤を作り、次女は毛利家を支える吉川元長(きっかわ もとなが。元就の孫)に、三女は宗家の毛利輝元(てるもと。元就の孫)に嫁がせることで、毛利一族の血縁強化に大きく貢献しています。
しかし、残念ながら元秀は病弱だったため廃嫡(はいちゃく。家督の継承権を剥奪)されてしまい、後に隆家が天正二十1592年に亡くなった時は、元秀の嫡男・宍戸元続(もとつぐ)が家督を継承しました。
子沢山だった以外にあまり詳しい記録が残っていない五龍姫ですが、そんな彼女の人柄や日ごろの振る舞いについて推測される、こんなエピソードが残されています。

時は元亀二1571年、死の床についていた父・元就が息子たちに対して「五もじ(五龍姫)は女のことゆえ、分別に欠けるところもあろうが、婿殿(隆家)ともども、妹弟と思って大切にしてやってほしい」といった旨を遺言。
このとき元就は75歳、五龍姫は43歳。いくら可愛い娘と言っても、既に立派な大人どころか、当時であれば初老の域に差しかかる年頃……よほど心配だった(女性である、という偏見を差し引いても、分別のなさが目に余った?)のでしょう。
婿の隆家にも気を遣っているところを見ると「ウチの娘がすみません」と思ってしまうような、気性の激しい嫁だったのかも知れません。
かつては「花よ、蝶よ」と育てられた姫が、嫁いでからは「龍よ、龍よ」と呼ばれる内、次第に龍のような激しさを備えていった……のだとしたら、まさに「名は体を表す」通り(レッテル効果)と言えるでしょう。
(※それで親族たちはあえて「龍」の字を避けて「五もじ」と呼んだのかも知れませんね)
大酒呑みだった?脳卒中で46歳の生涯を閉じるそんな五龍姫は天正二1574年7月16日、46歳の生涯に幕を下ろしましたが、その死因は脳卒中と言われています。
脳卒中と言えば、大酒呑みの代名詞……この当時、まだタバコは一般的ではなかったため、日頃から酒が好きだったのかも知れません。

「お方様、あまり御酒を過ぎると、大殿が心配なされまするぞ……」
父・元就は酒の害をよく知っており(父も祖父も酒毒が原因で早死にしている)、息子たちにはきつく禁酒の教訓を残していましたから、愛娘が大酒呑みだとしたら、その行く末を心配するのも当然です。
また、身分柄あまりあくせく動き回る必要もないでしょうから、慢性的な運動不足となれば当然(脳卒中の間接的要因である)肥満のリスクも考えられます。
加えて激しい性格となれば、過度のストレスを溜め込み、まさに脳卒中の数え役満。記録がないため確証はないものの、彼女が酒乱で夫・隆家に暴力など振るっていないことを願うばかりです。
ともあれ五龍姫は法光院殿栄室妙寿禅尼という戒名を授かりましたが、その墓所については諸説(4か所)あってハッキリとはしていません(あるいは分骨して、4か所ともなのかも知れません)。
ただ確かなのは、夫・宍戸隆家の墓が天叟寺跡(現:広島県安芸高田市)にあり、その隣にある唯一の墓碑は、彼の継室(後妻。石見繁継の娘)のものであるということ。
つまり一緒の墓には入っておらず、もしかしたら生前から疎まれてしまっていたのかも知れませんが、毛利家はもちろん宍戸家の繁栄にも大きく貢献した五龍姫ですから、あの世ではみんな仲良く暮らして欲しいと思います。
※参考文献:
安芸高田市歴史民俗博物館『毛利元就をめぐる女性たち』安芸高田市歴史民俗博物館、2012年
笠原一男『日本女性史3 彼岸に生きる中世の女』評論社、1973年
日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan














