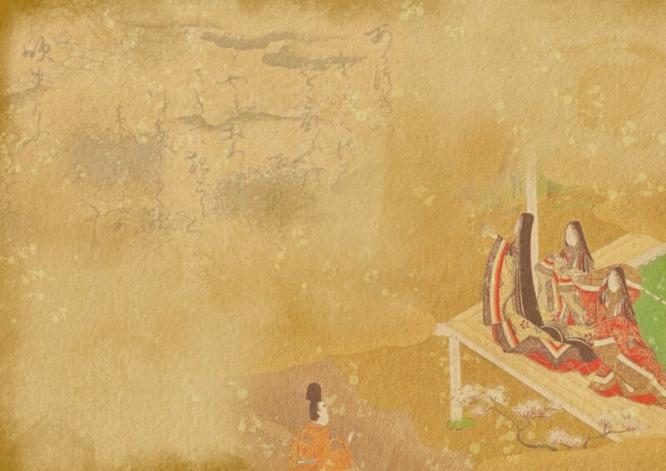「紐」は恋愛の象徴!日本古来から恋愛の機微の表現に使われた「紐」というコトバの美しさ

みなさんは、「和歌」がお好きですか?学生時代に百人一首を覚えたという方、和歌が多く登場する古典文学が好きという方、和歌にはあまり馴染みがないという方など、さまざまだと思います。
三十一文字という、決して多くない文字数のなかで、人々は自分の想いを表現しています。そこで、今回の記事では、そんな和歌の中から、「紐」という表現に注目していくつご紹介していきたいと思います。
ただ単に何かを結んでおくものとしての「紐」ではない、象徴的な意味合いが込められていました……!
昔の日本では「紐」が恋愛の象徴だった!?今を生きる私たちが「紐(ひも)」と聞いても、なかなか「恋愛」という言葉とはイメージが結びつきませんよね。しかし、和歌が多く読まれた奈良時代や平安時代においては、恋愛の機微を表す表現として、よく「紐」という言葉が使われていました。
以下、「紐」という言葉が登場する和歌をいくつか紹介しながら、その意味を探っていきたいと思います。
『万葉集』に登場する「紐」と「恋結び」奈良時代に成立した『万葉集』の巻12の2854番の歌に
白たへのわが紐の緒の絶えぬ間に恋結びせむ 会はむ日までに
というものがあります。
「白たへ」とは「真っ白な」、「絶えぬ間に」は「切れてしまう前に」、「会はむ日までに」は「また逢う日まで」という意味があります。
全体としての現代語訳は、「真っ白な私の着物の紐が切れてしまう前に恋結びをしておきましょう、また逢う日が来るまで」となります。
ここでの紐は下紐であり、いわゆる肌着・下着の紐です。当時は、男女がいっしょに朝を迎えた際、それぞれ自分の紐を結んでおいたという風習があったようです。
この歌では、その結び方について「恋結び」となっていますが、実はどのような結び方なのかはわかっていません。また、万葉集には多くの歌が詠まれていますが、「恋結び」という言葉が使われているのは、この一首だけななんだとか。
「恋結び」がいったいどんな結び方だったのか想像するのも楽しいですね。
源氏物語にも見られる「紐」源氏物語の「夕顔」の巻には、光源氏が詠んだ次のような歌があります。
泣く泣くも今日は我が結ふ下紐を いづれの世にか解けて見るべき
ここにも下紐という表現が使われています。この歌の現代語訳としては、「泣きながら、今日は私が一人でこの下紐を結んだとしても、いつの世に打ち解けてそれを解いてくれるあの人と逢うことができるのだろうか」となります。
この歌で光源氏が想っているのは、夕顔です。急死してしまった彼女の法要の際に、袴も作りました。その袴の紐を見て上記の歌を詠んだとされています。
いかがでしたか?この記事が、みなさんが少しでも日本文化や歴史の面白さに興味を持つきっかけになれば嬉しいです。
日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan