なろうと思ってなれるものではない 翻訳家という仕事 (1/3ページ)
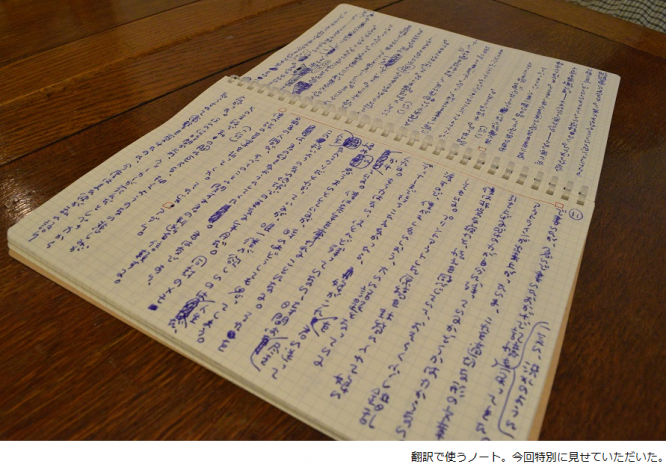
出版業界の最重要人物にフォーカスする「ベストセラーズインタビュー」。
2009年にスタートしたこの企画も、今回で100回目です。
節目となる第100回のゲストは、アメリカ文学研究者であり翻訳家の柴田元幸さんが登場してくれました。柴田さんといえば、翻訳書だけでなく自身が編集長を務める文芸誌「MONKEY」でも知られています。
今回はその「MONKEY」のお話を軸に、お仕事である翻訳について、そして研究対象であるアメリカ文学についてお話を伺いました。最終回の今回は、柴田さんが翻訳の世界に入ったいきさつを語っていただきました。(インタビュー・記事/山田洋介)
■「As if there were no tomorrow.」というつもりで ――柴田さんが翻訳の世界に入ったきっかけについてお聞きしたいです。柴田:なろうと思ったことはなかったんですよね。会計士や弁護士とちがって翻訳者は資格があるわけではないから、なろうと思ってなれるわけでもありません。
まして、僕が大学生や大学院生だった頃はポストモダン文学が全盛で、先端的なものは翻訳不可能に思えるような作品ばかりでしたから、全然なれる気がしませんでした。「翻訳の世界」という雑誌が当時あって、翻訳者の仕事がどんなものかはなんとなくわかったんですけど、それで食べていけるとは思わなかった。
ただ、とりあえず英文科に行って、その後に大学で英語やアメリカ文学を教えたりしていると、アルバイト的に翻訳の仕事が回ってくるんですよ。もちろん、最初は自分が訳したいものを訳せるわけではないけれど、そうやって回ってくる仕事をちゃんとこなしているうちに編集者からの信用みたいなものを得て、だんだんと自分のやりたいものができるようになっていきました。
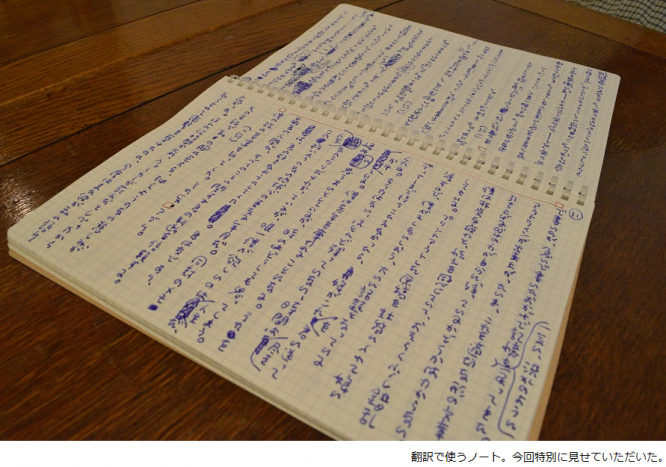
柴田:あとは運の部分も大きかったです。













