死を学ぶとは 学問としての死生学 (1/2ページ)
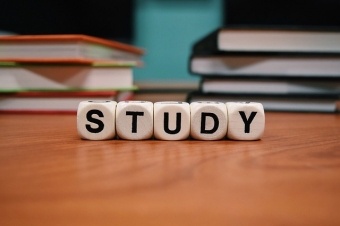
死にまつわる話題は、今でこそ「エンディングノート」「終活」といった言葉で日常的にも取り上げられるトピックになったが、長い間、避けるべき話題であり、実際に身内の死などに直面して初めて向き合うものであった。学問においても、宗教や哲学などの分野では「死」を扱うことはあったものの、それ以外の分野において死をテーマに論じることは好まれなかった。しかし、宗教学や哲学、社会学など様々な要素から死と向き合う「死生学」はゆっくりとその発展を続けてきた。
■老年学と共に始まった死生学
「死」に向き合うための学問「死生学」の起源は古く、1903年にロシア生まれの生物学者メチニコフが老年学(Gerontology)と同時に、死生学(Thanatology)という言葉を創出したことから始まっている。
その後、老年学は、高齢期をどう生きるか、生活(人生)の質(QOL、Quality Of Life)をテーマに社会的・心理的・哲学的に論じられ発展していったが、比較すると死生学の進捗は小さなものであった。
1990年代頃から、北米を主軸に死生学の研究が多く行われるようになった。死に対する不安や、社会的な捉え方の変化、死に直面している本人からその家族までをも研究対象とし、哲学や宗教学の範囲を超えて発展していった。死の質(QOD(D) Quality Of Dying and/or Death)という用語は死生学の用語である。
日本においては、1904年に仏教学者の加藤咄堂が「死生観」という言葉を使って、日本人としての死への向き合い方を記している。死の捉え方をさまざまな宗教や思想の特徴によって比較することで、武士道における死生観を説明した。
■さまざまな立場から見る死生学
その後、日本では度重なる戦争を経験する中で、戦争による死への向き合い方として「死生観」という言葉が用いられるようになる。この時代には、捕虜になることよりも自死(自決)を選択するなど、命の重みよりも個人の誇り、美意識が強調された。
戦後を経て1970年代頃からは、医療の発展に伴い、医師や看護師など医療者に死への向き合い方が求められるようになった。













