かつての金星は温暖な気候と水があり、生命が居住できる環境だった可能性が示唆される(米研究) (3/4ページ)
もしその後の30億年を地球のように進化したのであれば、二酸化炭素はケイ酸塩岩によって吸収されて地表に閉じ込められただろう。
そして7億1500万年前になる頃には、大気は大部分が窒素でそこに少量の二酸化炭素とメタンが含まれるといった地球に似たものになっていた可能性が高い。
なんとこの大気は現代にいたるまで安定して存在することもありえたらしい。つまり太陽系に地球のような惑星がふたつ存在する未来もあったのかもしれないのだ。
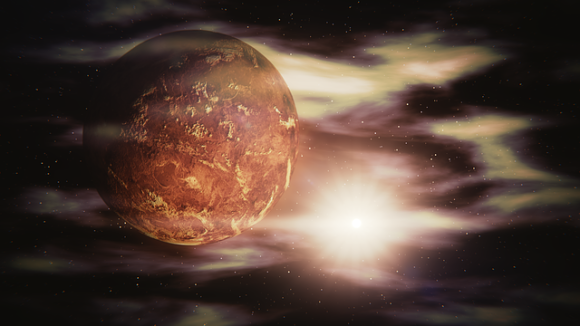
image credit:Pixabay
・火山活動で大量のマグマが煮え立ち灼熱の世界へと変貌か
ところが現実には大量のガスが噴出して金星は変貌してしまった。ガスが噴出した理由は謎に包まれているが、おそらくは火山活動と関係するのではと推測されている。
ひとつの可能性としては大量のマグマがぶくぶくと煮え立ち、そこから大気へと二酸化炭素が放出されたという状況が考えられる。
だが、そうしたマグマは地表に到達する前に固まってしまった。これが栓となり、放出されたガスは再吸収されなくなった。
こうして取り残された二酸化炭素が温室効果を発揮し、結果として現在の金星は平均気温462度という灼熱の世界へと変貌した。
また、金星が生命が住める惑星だったのかどうかをはっきりと知るためにまだ解明されていない疑問もふたつある。
ひとつは初期の金星が冷却された速さと、そもそも地表に水が液化したのかどうかということ。
もうひとつは金星全体で起きた地表の変化は一度きりだったのか、それとも長い時間をかけて繰り返し生じたのかということだ。













